中小企業の海外展開事例から学ぶ成功の条件とは|進出先の選び方や支援策も解説

INDEX ー
本記事では、成功事例と失敗事例の両面から、進出先の選定、戦略構築、人材体制、支援制度の活用までを具体的に解説します。海外市場に挑む中小企業が、持続可能な成長を実現するために必要な視点と行動指針を網羅しています。判断材料として、ぜひ参考にしてください。
成長を目指す企業が海外市場に挑む背景と今の動向
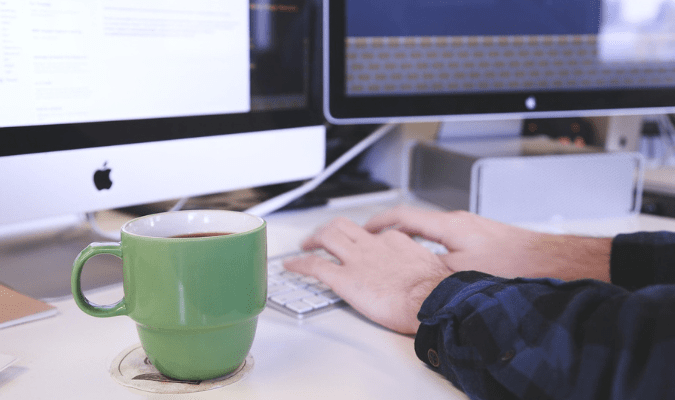
海外進出を図る中小企業が年々増加している背景には、国内需要の停滞や人手不足といった要因が存在します。とくに製造業や食品業などは、新興国を中心に成長市場を求めて活動を広げているのが現状です。市場開拓には課題もありますが、視点を変えれば新たな商機も見出せます。
ここでは、現状と進出の意義を整理し、読者が今後の戦略を描く土台となる情報を解説します。
なぜいま中小企業の海外進出が注目されているのか
人口減少や少子高齢化によって国内の消費が鈍化し、企業の成長機会は限定的です。一方で、アジアやアフリカなどの新興国では経済成長が加速し、中間所得層が拡大しています。
新興国では日本製品に対する信頼が高く、品質重視の傾向が根強いため、中小企業にも十分なビジネスチャンスが存在します。加えて、デジタル技術の普及によって国境を越えた販売やマーケティングのハードルが下がり、物理的な拠点を持たずとも商圏を広げられる状況が整ってきました。
従来は資金力や人材が必要とされていた海外展開が、今では規模を問わず取り組みやすくなっています。市場の変化に柔軟に対応できる中小企業こそが、グローバル化の波に乗る可能性を秘めています。
中小企業が海外進出するメリットについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
中小企業が海外進出するメリットとは|成果を最大化する戦略と経営者の心得
中小企業における海外展開の主な形態
進出の方法にはいくつかの選択肢があり、自社の状況や目的に応じて柔軟に選ぶことが求められます。代表的な形態には下記の3つが挙げられます。
- 輸出
- 現地法人の設立
- 技術提携
輸出は比較的ハードルが低く、越境ECを通じたテストマーケティングにも適しているでしょう。一方で、現地法人を設立するケースでは、現地スタッフの雇用や生産拠点の確保が必要になるため、より中長期的な視点での運営が求められます。
また、現地企業と提携することで、販路の拡大や商習慣への対応も効率的に進められるため、有力な手段の一つといえるでしょう。企業ごとの資源状況や事業目的に応じて、適切な進出形態を見極める判断力が不可欠です。
統計から見る中小企業の海外進出状況
中小企業の海外進出状況を見ると、大企業と比較して輸出・投資の比率が低いことが分かります。経済産業省の調査によれば、2021年度の大企業では輸出実施割合が約28%、投資割合が32%でした。一方で中小企業は輸出が21%、投資が14%にとどまり、海外展開は依然として限定的な傾向にあります。
参照:2024年版「中小企業白書」 第8節 海外展開 | 中小企業庁
業種別に見た進出傾向の違い
製造業の場合は、部品調達や現地生産によるコスト削減を目的とした進出が多くみられます。対照的に、食品業では現地消費者の味覚や嗜好に対応した商品開発が重要視されます。サービス業では、日本ならではの接客や技術力が差別化要因となり、教育・美容・医療分野などで高い評価を得ているのが特徴です。
各業種ごとに進出目的や課題が異なるため、戦略の立て方にも大きな違いが生まれます。共通して言えるのは、どの業種においても「現地のニーズを的確に捉える力」が問われるという点です。市場調査を重ねたうえで、商品やサービスの提供方法を最適化する必要があります。
進出先の選定で重視すべき要素とは
海外展開を検討する際には、進出先の選び方が成功可否に大きく関わります。市場規模の大きさや将来性だけでなく、治安、法規制、物流環境、言語、文化的な親和性といった要素を多角的に分析する必要があります。とくに、現地の法律や商習慣が自社に与える影響を見誤ると、予期せぬトラブルを招く可能性もあるので、注意が必要です。
また、過去に日本企業の進出実績がある地域では、情報や支援も得やすいため、初心者には適した選択肢といえます。地理的な距離や時差、通信環境もビジネスの継続性に影響を与えるため、総合的な視点で進出国を決定することが大切です。
進出先として注目される国と業種別の相性

進出を検討する際、どの国を選ぶかは戦略全体を左右する重大な要素です。市場の成長性だけでなく、法制度や文化、コスト構造なども含めた多角的な視点から選定することが求められます。
ここでは、実際に多くの中小企業が進出している地域の特徴と、自社に適した国を選ぶための判断材料を紹介します。
ASEAN諸国|進出数が多い理由と向いている業種
東南アジア地域は、多くの中小企業が海外展開先として選択している有力なエリアです。背景には、比較的近距離に位置することや、輸送コストが抑えられる物流インフラの存在が挙げられます。
さらに、多くの国で人口が増加傾向にあり、経済発展とともに購買力が高まっているため、消費市場としても大きな可能性を秘めています。現地の賃金水準が日本よりも低く、製造拠点の移転先としても高く評価されている点も特徴です。
とくに、タイやベトナム、インドネシアといった国々は、日系企業の進出が進んでおり、現地のビジネス環境も整ってきました。製造業や食品業、生活関連品を扱う企業にとって、ASEAN地域は成長と効率の両方を追求できる選択肢といえます。現地パートナーの確保や進出形態の見極めにより、成功の可能性がさらに高まるでしょう。
北米・欧州|ブランド力を活かしやすいマーケット
欧米地域は、品質や信頼性を重視する消費者が多いため、日本企業にとってはブランド価値を活かしやすい市場といえます。とくに北米は日本製品への信頼が厚く、現地市場において差別化が可能です。また、経済の安定性が高く、契約や知的財産に関する制度も整備されているため、ビジネス上のリスクを抑えやすいという特徴があります。
ただし、価格競争力が重視される分野では、他国との比較において苦戦を強いられる場面も見られます。したがって、製品・サービスに独自の価値を付加し、現地消費者のニーズに合わせたカスタマイズが重要です。
医療、教育、工業製品など高付加価値分野での展開を目指す企業にとっては、大きなビジネス機会が広がっています。信頼性と丁寧な対応力を強みにできる企業ほど、長期的に成果を上げやすいエリアといえるでしょう。
中国・韓国|文化・消費スタイルの近さを武器にする
中国や韓国といった東アジア諸国は、日本と地理的にも文化的にも距離が近く、比較的ビジネスが始めやすい地域とされています。
とくに消費者の嗜好が似ており、食文化や美容、生活習慣においても共通点が多いため、日本製品の受け入れられやすさが高い傾向にあります。また、観光によって日本に触れた経験を持つ層が増えていることも、販路拡大の一助になっているでしょう。
一方で、現地企業との競争が激しく、コスト面では現地ブランドに対して優位性を保ちにくい場面も見受けられます。価格だけで勝負するのではなく、安全性や機能性、デザイン性といった要素で訴求する必要があります。
加えて、政治的な動向や規制変更の影響を受けやすい点も念頭に置くべきです。柔軟なマーケティングと信頼関係構築が求められる市場といえるでしょう。
中東・アフリカ|成長市場としての可能性と準備すべきこと
中東やアフリカは、今後の人口増加が見込まれ、長期的には大きな市場規模を形成すると期待されている地域です。とくに中間層の拡大が進むことで、新たな需要が生まれつつあります。
中東やアフリカではインフラ整備や物流網が発展段階にあることが多く、進出には事前の調査と準備が欠かせません。輸出入の仕組みや現地パートナーの有無が、進出の成否を大きく左右する要素となります。
また、宗教や生活習慣が日本とは異なるため、製品開発やプロモーションにおいては文化的配慮が求められます。医療関連や教育支援、農業技術の分野では、日本の技術やノウハウが高く評価されるケースも少なくありません。リスクを踏まえた上で挑戦を決断すれば、他国と差別化されたポジションを築ける可能性があります。
国選びで重視すべき3つの視点
進出国の選定にあたっては、複数の要素をバランスよく評価することが不可欠です。まず第一に、市場の成長性とニーズの有無を見極める必要があります。ターゲット層が十分に存在しているか、将来的に需要が拡大する見込みがあるかといった観点から判断することが重要です。
次に、制度面や経済環境を確認し、法規制、税制、通関手続き、知的財産保護の状況などが自社にとって障害とならないかを検討する必要があります。さらに、自社の強みと進出先市場との相性を把握し、文化や消費スタイルとの整合性を検討します。
3つの視点を総合的に評価することで、失敗のリスクを抑えながら、より実行性の高い展開戦略を立てることが可能です。安易な感覚だけで国を選ばず、データと現地情報をもとに冷静な判断が求められます。
海外進出におすすめの国について、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
海外進出におすすめの国は?失敗しない選定基準と業種別ポイント
海外展開で成果を出した中小企業の成功事例
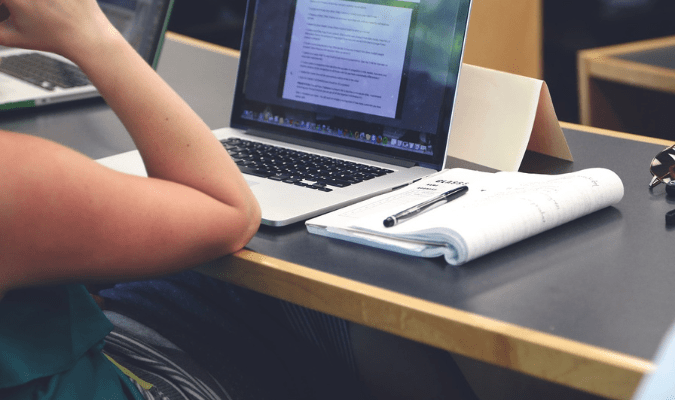
海外進出を成功させた中小企業には、それぞれ異なる背景や戦略があります。具体的な取り組みを知ることで、自社にとって参考になるヒントが見つかる可能性があります。ここでは、事例をいくつか紹介します。
エーエスジェイ株式会社
水処理機器を扱うエーエスジェイは、インドネシアの水普及率の低さに着目し、現地の学校へ浄水設備を導入するCSR活動から海外展開を始めました。クラウドファンディングや在校生による維持管理を取り入れた取り組みは、社会的価値を生みつつ収益化にも成功しています。
その後、JETROの専門家支援を活用し、現地金融機関や日本政策金融公庫から融資を獲得。2018年には現地への継続的な納品を実現し、中小企業ならではの柔軟性を武器に販路拡大を進めています。
株式会社花善
秋田県の老舗弁当メーカー花善は、看板商品「鶏めし弁当」を携え、パリ・リヨン駅で店舗を展開しました。現地の鉄道文化や食習慣に合う市場を徹底的に調査し、食材もフランスで調達する“地産地消”を実現しています。
専門家の助言を受けて規制や労務に対応しながら事業を軌道に乗せました。「地方からでも世界に挑める姿を示したい」という社長の強い信念が原動力となり、EKIBEN文化を海外に広める成功例となっています。
有限会社瑞穂
広島・熊野町の筆メーカー瑞穂は、化粧筆ブランドの国際的認知度を高めるため海外市場に挑戦しました。初出展では成果が出ませんでしたが、公的機関の支援を受けて展示会戦略や輸出体制を改善しています。
再挑戦の結果、OEM契約を獲得し、その後欧州展示会や自社ブランド「SHAQUDA」の立ち上げへと発展しました。SNSや直販サイトの活用も相まって、伝統工芸をグローバル市場に浸透させた好例といえます。
計画倒れを防ぐために知っておきたい失敗の傾向

海外進出には大きな成長の可能性がありますが、実際には多くの中小企業が撤退や縮小を余儀なくされています。事前準備や現地理解が不十分なまま進出したことで、計画通りに事業が進まず損失を抱えるケースも少なくありません。
ここでは、過去の失敗事例から見えてくる典型的なリスク要因を紹介し、どのような点に注意すべきかを整理します。
市場調査不足によるニーズのミスマッチ
ある日用品メーカーは、現地で人気が出そうな商品を輸出する計画を立てました。しかし、現地の生活習慣や使用環境を十分に調査していなかったため、実際に販売を開始しても反応は鈍く、在庫を大量に抱える結果となりました。
商品自体に問題があったわけではありませんが、需要のないものを届けてしまったことで、販路の拡大も進まず、短期間で撤退を決断せざるを得なかったのです。適切な市場調査を怠ると、商品と現地ニーズとの間にズレが生じ、どれだけ品質が高くても選ばれない状況に陥ります。
文化や気候、生活パターンなどを含めた総合的な分析を行うことが不可欠であり、現地に適した商品設計や販売方法の検討が求められます。単なる「輸出」ではなく「受け入れられる商品づくり」が前提であるべきです。
現地パートナーとの連携不全
ある日本の技術系企業は、販売チャネルの拡大を狙って東南アジアに進出し、現地代理店を通じて製品を展開しようとしました。しかし、現地パートナーとの連携体制が不十分で、商談フォローや納品管理にトラブルが多発したのです。
結果として、クレーム対応や納期遅延が重なり、ブランドイメージの低下を招いてしまいました。連携不全の原因には、目標設定や報酬体系のズレ、意思疎通の不足が挙げられます。事業の根幹を担う現地パートナーとは、単なる業務委託の関係ではなく、ビジョンを共有できる協働関係が必要です。
進出初期段階での信頼関係構築や業務ルールの明確化が不十分であれば、期待する成果は得られません。選定時には、実績やネットワークだけでなく、価値観の一致にも注目することが重要です。
自社に合わない進出形態の選択ミス
ある小売業者は、現地でのブランド展開を強化するため、いきなり直営店舗を複数開設するという大胆な方針を取りました。しかし、人材確保や店舗運営の知識が現地に不足していたため、運営コストが膨らみ、収益化の目処が立たないまま数年で撤退する結果となりました。
現地の法制度や雇用慣行を十分に理解していなかった点も、大きな障害といえます。進出形態の選定にあたっては、段階的なステップを踏むことが効果的です。たとえば、最初は輸出や現地企業との提携により様子を見ながら、市場の反応を見て次のステージへ進むといった慎重な方法が現実的です。
自社の経営資源や海外経験を冷静に見極めず、無理な展開を急ぐことで、損失が拡大するリスクが高まります。中長期的な視野での戦略設計が必要です。
価格競争に巻き込まれて利益を確保できなかった事例
ある金属加工企業は、現地の同業他社と価格帯を合わせることで販路を広げようとしました。当初は注文が増加し、順調な滑り出しを見せましたが、継続的な低価格での取引により利益が圧迫され、資金繰りが悪化してしまいました。
結果的に品質維持にも支障が出始め、最終的には競争力を失って撤退を余儀なくされたのです。価格のみで勝負を仕掛けると、資本力に勝る現地企業との競争で後れを取りやすくなります。
差別化のポイントが明確でない場合、価格が唯一の判断基準となってしまい、長期的には消耗戦に陥るおそれがあります。品質、納期、対応力など他の強みを活かし、価格以外の価値を提示することが必要です。安易な価格戦略は、中小企業にとって大きなリスクを伴います。
ブランドコンセプトの不一致による失敗要因
伝統工芸品を扱う企業が、欧州での販路拡大を目的に進出したものの、現地のデザイン感覚や価値観と乖離していたことで、ブランドが定着しませんでした。日本で高評価を得ていたデザインや機能性が、欧州市場では受け入れられず、見込み客に魅力が伝わらないまま販売不振に陥りました。
商品自体の品質には問題がなかったものの、訴求ポイントや表現手法が現地の消費者と噛み合わなかったことが原因です。海外展開では、単に製品を輸出するだけではなく、現地でどのような価値が認識されるかを考慮したブランディングが重要になります。
現地の文化背景や消費者心理を理解しないまま進出すると、魅力を正しく伝えることができず、ブランドとしての存在感を示せません。文化適応力が問われる場面といえるでしょう。
成果を引き寄せるための実践的な戦略と体制づくり

海外展開を成功させている企業の多くは、事前準備や進出後の対応力において明確な工夫を凝らしています。中小企業であっても、強みを活かしながら的確な戦略をとることで成果につなげることが可能です。
ここでは、よくある成功要因を具体的な視点から紹介し、再現性の高い行動指針として整理します。
現地市場に合わせた柔軟な商品開発を行う
海外市場で成功するためには、既存の商品をそのまま投入するだけでは十分とはいえません。現地の文化、嗜好、生活習慣などに応じた商品開発を行うことが大切です。たとえば、日本国内で人気のある味やデザインが、海外ではまったく評価されないケースも多くみられます。
成功している企業の多くは、現地のニーズを反映したローカライズを徹底しているのです。味付けの調整、パッケージの言語表記変更、サイズや色のバリエーションの追加など、細かな対応が購買率の向上に直結しています。
とくに食品や日用品などは、生活に密着しているため、違和感なく受け入れられる工夫が重要です。事前に現地消費者の声を収集し、テスト販売を通じて改善を重ねる姿勢が求められます。固定観念にとらわれず、柔軟な発想で商品を磨き上げましょう。
小規模から始めて段階的に展開を拡大する
リスクを抑えながら海外進出を実現するためには、一気に大きな投資を行うのではなく、段階的に展開するアプローチが有効です。多くの成功企業は、まず輸出やオンライン販売といったローコストな形態から海外市場にアプローチしています。
初期段階では、現地の反応を見ながら徐々に販売方法や商品内容を調整していくことで、無理のない範囲で市場理解を深められます。その後、成果が確認できた段階で現地法人の設立や合弁会社の設立など、より本格的な展開へとステップアップする方法が取られているのです。
段階的な進出スタイルは、経営資源の限られた中小企業にとっても現実的です。限られた予算の中でも、リスクを抑えつつ成果を最大化できる進め方を選びましょう。慎重なステップを踏むことが、長期的な安定につながります。
信頼できる現地パートナーとの関係構築を重視する
海外での販路拡大や事業運営を進める上で、現地パートナーの存在は非常に重要です。現地の商習慣や言語、法制度に精通したパートナーと協力することで、情報不足やトラブルのリスクを大きく軽減できます。
成功事例に共通しているのは、単なる業務委託の関係ではなく、長期的な協業関係を構築している点です。たとえば、販売戦略の共有や顧客対応の標準化などを進めることで、ブランド価値の維持や顧客満足度の向上につなげています。
また、トラブル発生時にもスムーズに対応できる体制が整っているため、事業継続性が高まります。パートナーの選定にあたっては、信頼性だけでなく、理念や目標を共有できるかどうかも重視しましょう。人間関係の構築も欠かせない要素として捉え、時間をかけた相互理解を深める姿勢が必要です。
現地文化や商習慣への理解を深める
海外展開では、製品やサービスの質だけでなく、現地文化への適応力も成功を左右する要素です。消費者の価値観や購買行動、商談時のマナーや契約の考え方などが自国とは異なるため、それらを軽視した対応をするとトラブルに発展する可能性があります。
成功している中小企業は、現地の文化背景や生活スタイルを深く理解し、それに基づいたマーケティングや接客手法を採用しています。たとえば、宗教や祝日に配慮した営業活動や、現地スタッフの働き方に合わせた組織体制の構築などが挙げられるでしょう。
現地との文化的なギャップを縮めることで、顧客との信頼関係を築きやすくなり、ブランドとしての受容も高まります。短期的な成果に目を奪われず、現地社会に根ざした姿勢を持つことが、長期的な成功へのポイントとなります。
海外展開に適した人材の確保と育成を行う
人材の質は、海外事業の成否を大きく左右します。現地とのやり取りやトラブル対応を担う人材が不在であれば、どれだけ良い戦略を描いても実行には結びつきません。成功している企業の多くは、語学力だけでなく、異文化への理解や柔軟な対応力を持った人材を育成・配置しています。
また、現地採用のスタッフに対しても、教育体制を整えることで、日本式のサービス水準や品質管理を維持しています。とくに中小企業の場合、限られた人数で事業を回す必要があるため、マルチなスキルを持った人材の育成が欠かせません。
海外対応に強い人材が社内にいることで、事業のスピード感や意思決定の精度も高まります。採用・研修・配置を一体的に計画し、組織として海外展開に対応できる体制を整えることが重要です。
海外展開に役立つ支援策と専門機関の活用法

海外展開を進めるにあたって、自社単独では対応しきれない場面が多々あります。そうした際に頼りになるのが、国や自治体、各種支援団体が提供している支援策です。制度を活用することで、情報収集や資金調達、パートナー探索などの負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、中小企業が利用しやすい代表的な制度や支援機関を紹介し、活用のポイントを整理します。
海外展開に活用できる主な公的支援制度
中小企業庁や経済産業省をはじめとした公的機関では、海外進出を目指す企業向けにさまざまな支援制度を用意しています。
タイミングを逃さず申請できるよう、情報を定期的に収集しておくと安心です。これらの制度は単なる金銭的支援にとどまらず、専門家とのマッチングやアドバイスも含まれている点が特徴です。制度をうまく活用すれば、進出準備の質を大きく高められます。
ジェトロの支援内容と活用方法
日本貿易振興機構(ジェトロ)は、海外進出支援に特化した国の機関として知られており、情報提供からビジネスマッチングまで幅広いサービスを展開しています。たとえば「海外ビジネスサポートセンター」では、法規制や市場動向に関する個別相談が可能です。
また、海外展示会への出展支援や現地企業との商談セッティングなど、実務に直結したサポートが整っています。さらに、貿易実務の研修や、輸出入に関するガイドラインの提供も行っており、初心者でも安心して取り組める体制が構築されています。
活用のポイントは、自社の課題に応じたサービスを選ぶことです。支援内容は非常に多岐にわたるため、まずは窓口で課題を共有し、最適なサポートを提案してもらうことが成功の近道となります。
商工会議所や自治体が実施する支援策
地元の商工会議所や各自治体でも、中小企業の海外展開を後押しする取り組みが進められています。とくに、地域ごとに実施されているセミナーや説明会、海外視察ミッションなどは、初めての進出を考える企業にとって有益です。
さらに、自治体によっては、進出費用の一部を助成する補助金制度や、専門家による個別相談サービスを提供しているケースもあります。地域密着型の支援は、企業の状況をより深く理解した上でアドバイスが受けられる点で優れています。
全国規模の制度と併用することで、よりきめ細かな準備が可能です。窓口との関係性を築いておくことで、緊急時の相談や最新情報の入手もしやすくなります。地元資源を最大限に活用する姿勢が、海外展開の基盤をより強固なものにします。
金融機関による資金面のバックアップ
海外展開には、現地調査や物流費、人件費など多くの初期費用が必要となるため、資金調達の手段も重要です。日本政策金融公庫や商工中金などでは、海外展開向けの融資メニューを用意しており、比較的低利で利用できるケースが多くあります。
また、民間の地方銀行や信用金庫でも、海外取引に対応したファイナンスサポートや、為替リスク対策の相談窓口を設けています。金融面の支援を受けるには、明確な事業計画書や進出スケジュールの提示が求められますが、準備を通じて事業の実現性を改めて検証する機会にもなるでしょう。
無理のない資金計画を立てることで、進出後の資金繰りにも余裕が生まれ、トラブルの回避につながります。資金面の支援も積極的に検討し、進出リスクを軽減しましょう。
支援制度を活用するための情報収集と準備
支援制度の存在を知っていても、実際に使いこなせている中小企業は多くありません。理由の一つが、情報の入手経路が限られていたり、申請に必要な準備が複雑であったりする点にあります。
したがって重要なのが、日頃から情報収集を継続し、制度ごとの申請要件やスケジュールを把握しておくことです。また、申請時には事業内容や進出の目的、必要経費などを整理した計画書の提出が必要となる場合が多いため、日常業務の中で資料作成の体制を整えておくとスムーズです。
専門家や支援機関の力を借りることで、申請の精度が上がり、採択の可能性も高まります。制度は知っているだけでは意味がなく、具体的な活用に落とし込んでこそ効果を発揮します。情報と行動の両輪を意識し、支援を最大限に活用しましょう。
まとめ
海外展開に成功している中小企業は、事前準備の質と進出後の柔軟な対応に明確な差があります。進出国の選定や文化への適応、現地パートナーとの信頼構築に力を入れる企業ほど、安定した成果を生み出しています。
また、失敗事例に共通するのは、現地理解や商品ローカライズの不足です。持続的な成長を実現するためには、自社に適した進出形態や人材体制を整えながら、公的支援制度や専門機関の力も取り入れる必要があります。
単独で解決できない壁が存在するからこそ、社外のリソースと戦略的に連携し、進出リスクを低減させることが現実的なアプローチとなります。中小企業が海外市場で挑戦を続けるためには、情報収集と戦略構築、そして行動を三位一体で進めていく姿勢が欠かせません。
監修者

岩﨑 正隆 / 代表取締役
福岡県出身。九州大学大学院卒業後、兼松株式会社にて米国間の輸出入業務や新規事業の立ち上げ、シカゴでの米国事業のマネジメントに従事。帰国後はスタートアップ企業にて海外事業の立ち上げを経験。自らのスキル・経験を基により多くの企業の海外進出を支援するために、2023年に株式会社グロスペリティを設立。

