日本企業の海外進出の現状とは|注目地域・業界別の傾向と成功要因を解説
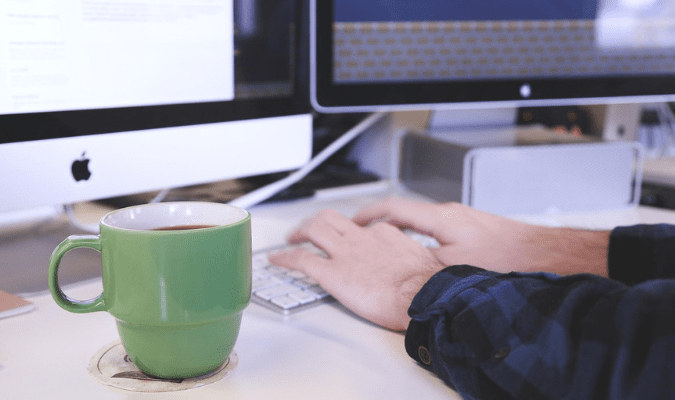
INDEX ー
ただし、進出には国ごとのリスクや市場特性への理解が不可欠です。成功を収める企業は、進出前に綿密な準備と戦略的判断を行っており、その姿勢が成果に直結しているのです。本記事では、最新データを基に、日本企業の海外進出の実態とその背景、地域別の動向、直面する課題、成果を上げるためのポイントまでを詳細に解説します。
日本企業の海外進出における現状とは

日本から国外への進出を目指す企業は近年増加傾向にあります。ただし、コロナ禍や為替変動など外的要因の影響もあり、単純に拠点数が増えているとはいえません。
地域や業界によって事情は異なり、実態を把握するには最新の情報が不可欠です。ここでは全体像として、拠点数の推移や形態の多様化、進出企業の属性などを具体的に見ていきます。
海外拠点数と進出企業数の推移
長期的な視点で確認すると、日本企業の海外展開は1990年代以降増加傾向にあります。外務省や経産省の調査によると、海外現地法人の総数は2020年時点で25,000社を超えています。支店や合弁事業、駐在員事務所なども含めると、拠点数は7万を上回る水準に達しているのです。
地域別に見る拠点の増減傾向
地理的な視点で分析すると、近年はアジア諸国への進出に対して見直しが進む一方で、中東や中南米、アフリカ地域への関心が徐々に高まっています。とくに中国における政治的リスクや市場成長の鈍化が懸念されており、拠点を縮小または他国へ移転する企業が増加しています。
対して、インドやUAE、ブラジルなどでは現地市場の成長期待やインフラ整備の進展から、新規進出や拠点拡張が活発化しているのです。北米地域については一定の需要が維持されており、とくに医療機器や食料品などの分野で進出が進んでいます。地域によって事業リスクと成長機会のバランスが異なるため、企業の意思決定には精緻な市場分析が必要です。
進出形態の多様化と越境ECの台頭
従来は現地法人や支店の設立が主流だった海外進出の形態に変化が生じています。とくにスタートアップや小規模事業者を中心に、越境ECやデジタル広告を活用した進出スタイルが広まりを見せています。
インターネット環境の整備により、現地に物理的な拠点を持たずとも製品を海外へ届けられる手段が整ってきました。加えて、SNSを活用したブランディング施策やインフルエンサーとの連携が販路拡大に寄与しています。
したがって、進出のハードルが下がり、とくに消費財を扱う業種において参入が加速しています。ただし、現地の法制度や消費者動向に関する理解が浅いままではトラブルにつながるため、戦略立案には慎重さが必要です。
海外進出が盛んな日本企業の業種とその特徴

進出企業の業界構成を見ることで、海外展開に適した業種の特徴が明らかになります。市場環境、業務特性、人材との相性などが影響するため、業界によって進出のしやすさが異なります。ここでは代表的な業界の動向を挙げつつ、それぞれが選ばれる理由を具体的に見ていきましょう。
製造業が根強い理由と工場展開の狙い
製造業は日本企業の海外進出において最も長い歴史を持つ分野の一つです。とくに自動車、電子部品、化学製品などの業種では、現地での生産拠点を設けることが定着しています。人件費の安さを求めてアジア諸国に工場を設立し、コスト削減と供給網の強化を実現してきました。
また、現地調達率を高めることにより、関税負担や為替リスクの軽減にもつながっています。製造業が進出先として選ぶ国は、技能人材の確保がしやすく、インフラが整備されているという点が特徴です。
生産拠点を海外に持つことは、事業の柔軟性を高める効果もあります。とくに複数国に分散して拠点を置くことで、災害や政変といったリスクへの対応力も強化されます。
IT・通信・サービス業の伸長背景
情報通信やシステム開発を中心としたIT業界は、近年になって海外展開を加速させている分野です。主な理由としては、現地の人材を活用することで開発コストを抑えられる点が挙げられます。
インドや東南アジア諸国ではエンジニア育成に力を入れる国が多く、技術力の高い人材を確保しやすいという点がメリットです。加えて、テレワークやクラウド環境の普及が進み、地理的な制約を受けずに業務を進められるようになったことも追い風となっています。
サービス業においては、語学対応や現地スタッフの教育によって質の高い顧客対応が可能になるため、競争力を維持しやすくなります。今後もデジタル分野を中心とした進出は、業界全体の変革を促す可能性があるでしょう。
卸売・小売業が勢いを増す理由
近年の調査では、卸売業および小売業が海外展開に積極的な動きを見せていることが明らかになっています。背景には、為替の動向や越境ECの普及によって、現地販売へのハードルが下がってきているという事情があります。
とくにD2Cブランドや個人経営レベルの事業者でも海外販路を開拓できる環境が整い始めており、従来型の流通構造にとらわれない戦略が必要です。また、アジアや北米市場では日本製品に対する信頼感が強く、高品質な商品が高価格帯でも受け入れられやすい傾向があります。
物理的な出店に加えて、ECモールや現地マーケットプレイスを活用することで、効率的な市場参入が実現可能です。販路多様化によるリスク分散も見逃せないポイントといえるでしょう。
医療・人材・教育など成長産業の傾向
医療や人材紹介、教育関連などの分野は、新興国を中心に需要が拡大している業界です。とくに医療機器や検査装置などは、高齢化の進展や医療制度の整備が進む地域で注目度が高まっています。
人材サービスは、日系企業の現地採用や教育支援を目的とした進出が目立ってきている点も特徴です。教育業界では、日系の学習塾や語学教育機関がアジア諸国で存在感を強めており、日本の教育メソッドへの関心が高まっている様子がうかがえます。
現地社会の課題解決と直結する性質を持つため、政府からの支援や優遇措置を受けやすいという利点もあります。社会貢献とビジネスの両立を意識した展開が求められる領域です。
業種ごとの動向とポイントについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【業界別】海外進出の最新動向と成功のポイント|チャンスがある分野やリスクも解説
日本企業が進出している国・地域の最新傾向
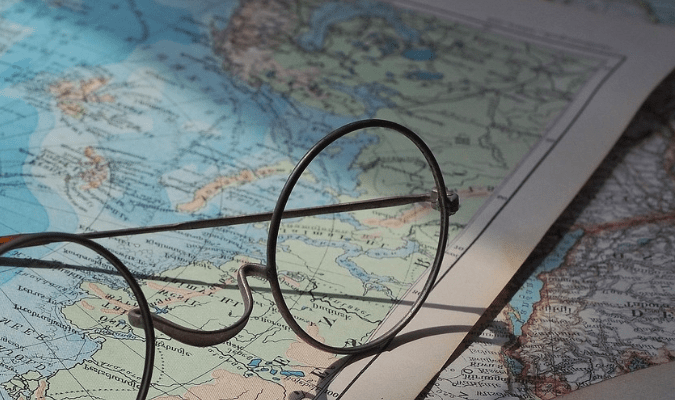
進出国の選定は、海外展開の成否に大きく影響します。市場規模や法制度の安定性、現地ニーズの変化に対応する柔軟性が問われるため、特定の地域に偏ることはリスクにもなりかねません。ここでは、近年注目されている国や地域の傾向について、最新データを踏まえて解説します。
ASEANとインドの存在感の高まり
アジア地域の中でも、ASEAN諸国およびインドへの進出は継続的に増加傾向を見せています。経済成長が著しいインドでは、豊富な若年人口と拡大する中間層によって、内需型ビジネスの展開が見込まれています。
とくにITやヘルスケア、消費財分野での需要が急増しており、日本企業にとって魅力的な進出先です。ASEAN地域では、タイやベトナムを中心に製造業をはじめとした日系企業の集中が進んでおり、現地インフラの整備やFTA(自由貿易協定)による取引条件の緩和が進出を後押ししています。
さらに、文化的な親和性や人件費の優位性も支持される要因として挙げられます。安定した政治体制を持つ国を中心に、今後も日本企業の動きは加速するといえるでしょう。
アメリカが注目される背景
アメリカ市場は依然として世界最大規模の消費地として、日本企業にとって魅力的な進出先のひとつと位置付けられてきました。購買力の高い層が厚く、現地法人の展開やECビジネスの構築に向いた環境が整備されている点が、参入障壁を乗り越える要因です。
ただし、2025年以降の関税政策は、進出企業にとって大きなリスクとして浮上しています。とくにトランプ政権が再導入した「相互関税制度」により、日本製品の一部に最大15%の追加関税が課される状況が現れています。自動車関連や鉄鋼、電子部品など主力製品群が対象とされることで、価格競争力の低下を招く恐れが広がりました。
さらに、関税緩和を受けるには日米間での交渉合意が必要となり、進出企業には継続的な政策動向の把握と調整が求められます。輸出依存度が高い製造業にとっては、影響範囲の大きさが無視できません。したがって、進出を検討する段階から関税対応を視野に入れた事業設計を行うことが、今後いっそう重要になります。
中国・香港への警戒感と再編の動き
かつて日本企業の主要な進出先として高い人気を誇っていた中国や香港に対しては、現在やや慎重な姿勢が目立ち始めています。政治情勢の不安定化や規制強化の影響によって、現地ビジネスの先行きに不透明感が漂っているためです。
とくに2020年代に入ってからは、日系企業による拠点縮小や撤退の動きが複数報告されています。また、製造業を中心に他国へのシフトが進み、インドやベトナム、インドネシアへの再配置が目立っています。
コスト競争力の高い中国企業の台頭も、日本企業にとっては脅威となっており、価格以外の付加価値による差別化が必要です。依然として巨大市場であることに変わりはありませんが、従来のような安定成長を前提とした戦略は見直されつつあります。
中東・アフリカ・中南米など新興国の注目度
既存の主要市場以外にも、非伝統的な地域への進出が徐々に増加しています。中東ではUAEを中心に、物流や建設、エネルギー分野での進出が目立ちます。
アフリカ地域では南アフリカ共和国やケニアが代表的な進出先となっており、現地経済の発展とともに教育や医療分野のニーズも高まっているのです。また、中南米ではブラジルやメキシコへの進出意欲が高まっており、とくに食品関連やインフラ整備における需要が顕著です。
これらの地域は地政学リスクが残る一方で、高成長余地の大きさから魅力的な投資対象として認識され始めています。従来の定番地域とは異なる戦略や準備が求められますが、リスク分散の観点からも新興国への進出は選択肢として無視できない存在となっています。
国ごとの事業拡大意欲と黒字率の違い
地域別に業績や事業拡大の見通しを比較すると、明確な違いが浮かび上がります。中国や香港では拡大意欲が著しく低下しており、これまでと比較して慎重な姿勢が目立ちました。利益面では、南アフリカやUAEなどで高い黒字率が報告されており、特定の業界においては非常に高い収益性が期待されています。
ただし、黒字率が高い国が必ずしも進出しやすいとは限らず、現地の制度や競合状況、文化的背景なども考慮する必要があります。各国の特性を理解したうえで、戦略的にリソースを配分することが長期的な成功につながるでしょう。
日本企業が海外進出で直面している課題とは

海外展開には多くの可能性がある一方で、想定外の障壁に直面することも少なくありません。事前準備やリスク管理が不十分な場合、想定した成果を上げることは難しくなります。ここでは、海外進出を進める上で頻繁に見られる課題について、分野ごとに整理して見ていきます。
競争環境の激化とコスト圧力
多くの国では、日本企業だけでなく現地企業や欧米企業との激しい競争が発生しています。とくに新興市場では、価格競争がビジネス継続の足かせになることが目立っています。中国系の企業はコスト優位性に強みを持ち、欧米企業はブランド力やマーケティング力を武器としているのです。
競争環境の激化で、日本企業は付加価値のある製品やサービスを展開しない限り、価格面で太刀打ちするのは難しくなります。また、インフレや為替変動による調達コストや物流費の増加が経営を圧迫し、現地価格への転嫁が困難な状況も多く見受けられます。
競争環境が過酷な市場においては、差別化戦略の構築とともに、現地コスト構造に対応した柔軟な価格設定が必要でしょう。
現地人材の確保と育成の難しさ
現地での事業運営において、人的資源の確保と育成は重要な要素です。ただし、日本企業にとって現地の人材採用は一筋縄ではいかないケースが多く見られます。たとえば、言語や価値観の違いから円滑なコミュニケーションが取れず、業務効率やモチベーションの低下を招く場合があります。
また、リーダーシップを担える現地幹部の不足や、雇用契約の法的制約に悩まされることも少なくありません。さらに、日本本社との連携がうまく機能しないことが、離職率の高さや人材流出の一因となっています。
海外進出ならではの課題に対応するためには、ただの採用にとどまらず、現地文化への理解を深めた上での教育制度やキャリアパス設計が必要です。
法制度・規制対応の難易度
進出先の国によっては、法律や規制の内容が頻繁に変更されることがあります。とくに新興国では、外資企業向けの制度が未整備または不透明なケースも多く、企業活動に大きな影響を及ぼすことがあります。
たとえば、税制変更や関税の引き上げ、ライセンス取得要件の変更などが突如として実施されることで、当初の事業計画が大きく狂う可能性も否定できません。さらに、汚職や不正な慣習がビジネスの進行を妨げる事例も少なからずあります。
こうした背景を踏まえると、進出の際には信頼できる現地専門家やリーガルパートナーと連携を取り、常に最新の情報を把握しておくことが欠かせません。法的リスクへの備えが不十分な場合、撤退や損失のリスクが高まります。
文化・商習慣の違いによるトラブル
海外市場で事業を展開する際には、文化的背景や商習慣の違いに起因する誤解や摩擦が発生することがあります。たとえば、契約や納期に対する考え方、交渉の進め方、意思決定のスピードなどが日本とは大きく異なる場合があります。
日本的な丁寧さや品質へのこだわりが現地で必ずしも評価されるとは限らず、顧客とのすれ違いやトラブルにつながることもあるでしょう。また、宗教や祝祭日への配慮が欠けることで信頼を損なうケースも報告されています。
問題を未然に防ぐためには、現地文化を深く理解し、現地スタッフの声を反映した柔軟なビジネス運営が必要です。画一的な日本式アプローチではなく、多様性に配慮した対応が求められます。
撤退リスクと失敗事例の傾向
海外進出には多大な準備と投資が伴うため、万が一の撤退は企業にとって大きな打撃となります。実際、現地での収益性が見込めず撤退を余儀なくされた事例も少なくありません。失敗の要因としては、市場調査の不足、現地ニーズとのミスマッチ、競合の過小評価などが挙げられます。
また、為替リスクや政治的不安定さといった外的要因による撤退も多く報告されています。とくに拠点の設立を急ぎすぎた結果、柔軟な対応が取れずに撤退せざるを得なかった企業は少なくありません。
事前にリスクシナリオを描き、撤退基準を明確に設定することが、損失最小化の観点からも重要となります。進出だけでなく、適切な「出口戦略」を持つことが安定経営につながります。
海外進出における課題について、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
海外進出における企業の課題は?解決策や成功事例、注意点を解説
海外進出で成果を上げる日本企業の共通点と準備

海外市場で安定した成果を上げている日本企業には、共通した傾向がみられます。進出先の特性やリスクに対する理解が深く、事前の準備を丁寧に行っていることが成功要因となっているようです。
ここでは、成功している企業の行動パターンと、進出前に意識すべき具体的な準備について解説していきます。
市場調査とローカライズ戦略の徹底
成果を出している企業の多くは、現地市場に関する徹底的なリサーチを行っています。人口動態、消費習慣、競合環境など、複数の要素を分析した上で自社製品やサービスの受容性を見極めてから事業を展開しています。
また、提供する商品やサービスを現地のニーズに合わせて調整している点も見逃せません。たとえば、味付けやデザイン、パッケージ、価格帯など、消費者の好みに合わせて最適化を行うことで、高い評価を獲得している例が数多くあります。
言語や広告表現においても、直訳ではなく文化に即した表現を採用することで、親近感や信頼感を高めています。市場とのミスマッチを避けるためにも、ローカライズは単なる翻訳ではなく戦略的に実施することが欠かせません。
現地パートナーとの連携が成功を左右する
現地の状況に精通しているパートナー企業と連携することで、事業展開が円滑に進むケースが多く見受けられます。とくに販路開拓、法務対応、人材確保といった分野においては、外部の協力なしに自社だけで対応するのは非常に困難です。
信頼できるパートナーを見つけることは、成功の土台づくりに直結します。また、現地企業と協業することで商慣習や文化の違いを埋めやすくなり、トラブル回避にもつながるでしょう。
さらに、合弁会社の設立やフランチャイズ展開など、パートナーシップの形態も柔軟に検討されています。短期的な成果だけでなく、中長期での事業安定を目指すなら、信頼関係を重視したパートナー選定が必要不可欠です。契約条件だけでなく、価値観の共有も重要な判断基準になります。
柔軟な組織体制とグローバル人材の活用
海外事業を支える組織体制には、高い柔軟性が求められます。国内のやり方をそのまま持ち込むのではなく、現地の文化やビジネス環境に応じて体制を組み替える企業が成果を上げているのです。たとえば、現地に意思決定権を委ねることで、素早い対応と独自の工夫が可能です。
また、海外経験を持つ人材や多言語対応ができるスタッフの起用が、現地との橋渡し役として機能しています。最近では、外国籍社員を積極的に登用し、異文化に強い組織風土を育てる取り組みも進んでいます。
社内でのグローバル教育やOJT制度を整備し、現地法人と本社が協調できるような人事制度を構築することで、持続的な成果につながりやすくなるでしょう。組織の硬直化を防ぎ、多様な働き方を認める姿勢が重要です。
越境ECやSNSなどデジタル施策の有効性
オンライン環境の整備が進んだことにより、現地に物理的な拠点を持たずとも海外展開が可能な時代となりました。とくに中小企業やスタートアップにとって、越境ECやSNSを活用した進出はコストを抑えつつ広範な市場へのアプローチを可能にしています。
たとえば、AmazonやShopeeといった現地ECモールを通じて商品を販売し、現地言語でのSNS広告やインフルエンサーを活用する手法が一般的になっています。また、口コミやレビューの管理にも力を入れることで、顧客の信頼を獲得しやすいでしょう。
デジタル施策は施策の効果を可視化しやすいため、マーケティング戦略の最適化にも貢献します。短期的な販売促進にとどまらず、ブランディングやファン層の形成にもつながる取り組みとして注目されています。
小規模でも実行可能な低リスク進出モデル
小規模な企業でも実現可能な海外展開の方法が整ってきたことで、参入障壁は大きく下がりました。とくに最近では、テスト販売を行いながら徐々に販路を拡大していく段階的なアプローチが注目されています。
リスクを抑えるために、越境ECを入り口にして市場の反応を確認し、その後パートナー企業と連携して現地代理店契約を結ぶなどのモデルが採用されています。さらに、現地法人を設立せずに実務を進めるバーチャル進出も一部で活用されており、初期投資を最小限にとどめる工夫が施されているのです。
重要なのは、いきなりフルスケールで展開せず、段階ごとに検証しながら進めることです。柔軟かつスモールスタートが可能な進出モデルは、リスク許容度の低い企業にとって有効な選択肢となっています。
まとめ
日本企業の海外進出は、過去数十年にわたって拡大を続けてきました。近年では進出地域や業界の多様化が進み、製造業に加えてIT、サービス、小売、教育など幅広い分野で展開がみられます。
ただし、競争環境の激化や法制度の複雑さ、人材確保の難しさといった課題も多く、ただ拠点を増やすだけでは成果を上げることが困難になっています。成功している企業に共通するのは、市場調査を丁寧に行い、現地文化に配慮したローカライズ戦略を実行している点です。
さらに、現地パートナーとの連携や柔軟な組織体制、デジタル技術の活用によって効率的かつ持続可能な運営を実現しています。今後は成長市場を見極めた上で、適切な手法とリスク管理を重視することが求められます。戦略的な判断が将来の成否を左右するでしょう。
監修者

岩﨑 正隆 / 代表取締役
福岡県出身。九州大学大学院卒業後、兼松株式会社にて米国間の輸出入業務や新規事業の立ち上げ、シカゴでの米国事業のマネジメントに従事。帰国後はスタートアップ企業にて海外事業の立ち上げを経験。自らのスキル・経験を基により多くの企業の海外進出を支援するために、2023年に株式会社グロスペリティを設立。

